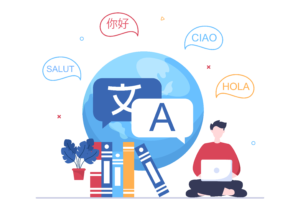こんにちは!グローハイ海外進出チームです。
海外展開を進める中で、「現地の実情がわからない」「ニーズに合った発信が難しい」と感じる企業は少なくありません。そうした課題の解決に役立つのが、現地の専門家に直接話を聞く「エキスパートインタビュー」です。
私たちグローハイでも、北米・欧州を中心に、各地域のエキスパートにインタビューを行い、マーケティング戦略や商品企画に活用しています。
実際にエキスパートインタビューを通じて得られたリアルな声や具体的な知見は、机上の調査では得られない“生きた情報”であり、多くのクライアント企業からも「現地理解が一気に深まった」「社内を説得する材料になった」といった高い評価をいただいています。
この記事では、エキスパートインタビューの活用方法や実施のポイント、具体的な事例までを簡潔にご紹介します。海外市場を深く理解し、戦略や発信の質を高めたい方は、ぜひご覧ください。
■グローハイでは海外オンライン展示会「VirtualExpo(ヴァーチャル・エキスポ)」の出展をサポートしています。
VirtualExpoは機械、建築、造船、医療、農機、航空の6分野における製造業のBtoB専門オンライン展示会です。
欧州や北米、南米、さらにはアジア、中東アフリカ等にもリーチ可能なオンラインによるビジネスマッチング・プラットフォームです。欧州バイヤーが半数以上を占めるVirtualExpoに出展することで、欧州を始めとする世界各国・地域への販路開拓が可能となります。
出展するには英語対応が必要で、グローハイでは日本企業様のVirtualExpoの営業窓口を担っております。
目次
第1章:海外調査におけるエキスパートインタビューとは
・なぜ今「定性調査」が重要なのか
・エキスパートインタビューの定義と海外展開への有効性
・定量調査や市場データと補完し合うアプローチ
第2章:主な活用目的|戦略立案と信頼性のある情報発信
・① 現地理解を踏まえた意思決定・戦略判断への活用
・② 対外発信における信頼性強化と差別化
・上記2軸以外の展開可能性
第3章:実施フローと設計のポイント
・海外インタビュイーの選定・アプローチ方法
・目的に応じた質問設計と情報の引き出し方
・実施形式(オンライン・文面・通訳あり)の選び方と注意点
・意思決定支援につながる社内資料化とナレッジ共有
・社外への発信・ブランディングにも活かせる素材へ
・エキスパートインタビューから得られた3つの実践事例
第5章:海外調査としての価値と投資対効果の高め方
・単発調査に終わらせない情報活用の循環設計
・外部調査会社・ローカルパートナーとの連携
・多言語・多文化への対応と編集の工夫
第1章:海外調査におけるエキスパートインタビューとは
なぜ今「定性調査」が重要なのか
海外市場に進出する際、企業は多くの情報を必要とします。たとえば、消費者のニーズや文化的な背景、業界構造や流通チャネル、競合企業の動き、行政規制の実態など、幅広く複雑な要素が絡み合っています。
こうした情報を得るには、政府統計や業界レポート、データベースなどを用いた定量調査(数字で把握できる調査)が基本ですが、それだけでは把握しきれない「現地の空気感」や「リアルな現場の判断基準」は多く残ります。
たとえば、
- 「A国で自社製品が売れない理由は、価格帯ではなく文化的な好みに起因していた」
- 「競合が進出していないのは市場性がないからではなく、認可の取得が難しいからだった」
といった事実は、定量的なデータだけでは読み解けません。
こうした背景から、現地の専門家の声を直接聞き、状況を立体的に理解する“定性調査”の重要性が、あらためて注目されています。
その代表的な手法が「エキスパートインタビュー」です。
エキスパートインタビューの定義と海外展開への有効性
エキスパートインタビューとは、特定分野の知見を持つ専門家(研究者・業界関係者・実務家など)に対し、あるテーマについて深く聞き取りを行う調査手法です。
海外市場における活用では、たとえば以下のようなケースで行われます。
- 現地の業界動向や商習慣について、ローカルコンサルタントや業界関係者に聞く
- 消費者の嗜好や価値観の変化について、マーケティング研究者にインタビューする
- 販売チャネルや価格戦略の実態について、小売業者やディストリビューターに聞く
- 進出障壁(規制・許認可など)について、弁護士や行政書士にヒアリングする
こうした聞き取りを通じて、企業は「自社にとってのリスク」や「進出の可能性」「競争上の立ち位置」などを、定性的に理解することができます。
また、現地語での調査が難しい場合でも、通訳を挟む形で実施可能であり、グローバル展開を見据えた初期リサーチの選択肢として有効です。
定量調査や市場データと補完し合うアプローチ
エキスパートインタビューは、それ単独で調査を完結させるというよりも、既存の定量データやレポートと「補完関係」にある調査手法です。
たとえば、
- 定量データで市場成長率や競合シェアを把握したうえで、「なぜこの数字になっているのか?」をエキスパートに聞いて裏付ける
- アンケートで得られた消費者の声に対し、現地マーケターに「背景にある文化的価値観」を聞くことで深く解釈できる
- 公的な制度や統計上は問題なさそうな点について、「実務上はどう運用されているか?」という実態を現地の弁護士や企業担当者に聞いて明らかにする
といった使い方が可能です。
このように、数字で捉えた「What(何が起きているか)」に対して、「Why(なぜそうなのか)」を補完するのが、エキスパートインタビューの大きな役割です。
特に言語・文化・商習慣が大きく異なる国や地域への展開では、こうした「現地の知」との接続が、戦略の精度を高める決定的な要素となります。
第2章:主な活用目的|戦略立案と信頼性のある情報発信
エキスパートインタビューは、単なる聞き取りにとどまらず、企業の海外展開を多角的に支える戦略的な情報資源として活用されています。本章では、その活用目的を大きく二つの軸に分けて整理し、さらにその発展可能性にも触れます。
① 現地理解を踏まえた意思決定・戦略判断への活用
第1章で述べたとおり、エキスパートインタビューは「なぜその現象が起きているのか」という背景理解に有効です。しかしその意義は、単なる知識獲得にとどまりません。企業の実務における意思決定の質を高めるための情報として、次のような形で活用されます。
- 戦略方針の妥当性検証
たとえば進出市場の選定やターゲット層の見極めにおいて、現地の見解を取り入れることで、社内での仮説や方針に対する裏付けや修正が可能になります。 - 社内合意形成の促進
客観的な第三者視点があることで、社内関係者への説得材料となりやすく、プロジェクトの合意形成や決裁プロセスをスムーズに進める一助になります。 - 進出障壁・リスクの先読み
表面的には見えづらい制度運用のギャップや業界特有の非公式ルールなど、現地事情を反映した「実務上の注意点」を早期に把握できます。
このように、エキスパートの見解を活かすことで、戦略の精度や実行力そのものを高めることができるのです。
② 対外発信における信頼性強化と差別化
エキスパートインタビューの活用は、社内の判断材料にとどまらず、海外市場に向けた情報発信の質を高める手段としても有効です。とくにBtoB領域では、情報の信頼性が意思決定に直結するため、次のような活用方法が注目されています。
- コンテンツの説得力向上
ホワイトペーパーや業界レポート、ブログ記事などにエキスパートのコメントを引用することで、単なる自社目線の情報ではなく、「中立性のある一次情報」としての価値が加わります。 - 現地理解の深さを示すブランディング効果
海外市場に対する本気度や理解度を示す要素として、現地専門家との対話をもとにした発信は、取引先やパートナーに安心感を与えます。 - SNSやメールマーケティングでの差別化コンテンツ
インタビュー結果を活用したコンパクトなコラムやインフォグラフィック、動画コンテンツは、現地ニーズやトレンドを反映した「刺さる情報」として拡散性が高く、マーケティング施策に組み込む企業も増えています。
このように、信頼性の高い情報発信は、単なるPRではなく、現地市場へのリーチと反応を高めるマーケティング戦略の一部として機能しています。
上記2軸以外の展開可能性
エキスパートインタビューは、戦略立案や情報発信だけでなく、以下のような場面でも多面的に活用されています。
- 営業活動における信頼構築
提案資料や商談時のトークの中で、現地エキスパートの意見を引用することで、顧客の共感や納得を得やすくなります。 - 社内教育・人材育成コンテンツへの転用
海外業務に不慣れなメンバーにとって、専門家の見解は“生きた教材”として機能し、異文化理解や業界知識の習得に役立ちます。 - IR資料やステークホルダーへの説明補強
海外展開の裏付けとして、エキスパートの意見は客観的な根拠となり、投資家や社外関係者への信頼構築にも寄与します。
エキスパートインタビューは、定性調査としての価値にとどまらず、企業の実務に即した活用によってこそ真価を発揮します。現地の文脈を理解し、戦略に落とし込み、信頼性の高い情報として社外へ発信する──その全プロセスにおいて、エキスパートの知見は、企業にとって極めて重要な資源となっています。
第3章:実施フローと設計のポイント
エキスパートインタビューを有効に機能させるには、「誰に・何を・どうやって」聞くかの設計が重要です。本章では、インタビューの成功率を高めるための具体的な実施フローと設計ポイントを紹介します。
① 海外インタビュイーの選定・アプローチ方法
● どんな相手を選ぶべきか
インタビュイーの選定は、調査の質を左右する最重要工程です。以下の観点から、目的に応じた相手を見極めましょう。
- 業界の構造や商習慣を知りたい場合:現地業界団体、コンサルタント、商社の営業責任者など
- 消費者トレンドを把握したい場合:マーケティング研究者、小売現場の責任者、ローカルインフルエンサーなど
- 制度・規制の実態を知りたい場合:行政書士、現地の弁護士、法務担当者など
- 販売チャネルの実務を知りたい場合:流通業者、小売チェーンの購買担当など
● アプローチの方法と注意点
- LinkedInなどのビジネスSNSの活用:英語圏・欧州では有効。メッセージ文では調査目的と活用範囲(例:社内資料用など)を明記。
- 業界展示会・カンファレンスでの接触:その場で面識を作り、後日インタビュー依頼につなげる。
- 現地パートナー・通訳者経由の紹介:信頼性が高く、アポ取得率も上がる。
ポイント:報酬の有無や匿名性の有無を明確に提示し、相手の負担やリスクを最小化する工夫が必要です。
② 目的に応じた質問設計と情報の引き出し方
● 質問設計の基本構造
- 導入部(アイスブレイク+経歴確認)
例:「この分野で何年ほどご経験がありますか?」 - 本題(仮説に基づいた深掘り質問)
例:「この製品カテゴリーは近年、誰が主要な購買層ですか?」 - 補足・裏付け(エピソードや数値)
例:「その傾向が分かるような具体例はありますか?」
● 引き出す力=“深掘り”+“比較”
- 「なぜそう感じますか?」「もしAではなくBだったらどうなりますか?」
- 「他国と比べてどうですか?」「以前と比べて変化はありますか?」
ポイント:Yes/Noで終わらない設計が、価値ある定性情報を引き出す鍵となります。
③ 実施形式(オンライン・文面・通訳あり)の選び方と注意点
● 実施形式の選択肢
| 形式 | 特徴 | 向いているケース |
| Zoom/Teams等のオンライン | 表情やニュアンスを把握しやすい | 初対面・複雑なテーマ |
| メール・Googleフォーム等の文面形式 | 時間調整が不要・記録が残る | 補足調査・フォローアップ |
| 通訳ありの対面・オンライン | 言語の壁を越えられる | 現地語必須・重要な判断前 |
● 注意点と対策
- 通訳を挟む場合:事前に用語リストと調査意図を共有することで精度を高める
- 録音・録画の許可:文化や国によっては慎重な配慮が必要。必ず事前に同意を得る
- 回答の偏り防止:特定のバイアスがかかる立場(ベンダー・販売側など)の場合は複数名の意見で補完する
エキスパートインタビューは、準備段階の設計で結果が大きく変わります。インタビュイーの選定・質問の設計・実施方法を戦略的に組み合わせることで、より深く、実務に活かせる知見を得ることが可能です。
次章では、実際にエキスパートインタビューを行った企業の活用事例を紹介し、具体的な成果や工夫点に迫ります。
第4章:得られた知見の活用|社内外への転用と資産化
① 意思決定支援につながる社内資料化とナレッジ共有
エキスパートインタビューの一次情報は、事業部門や経営陣の判断材料として活用できるよう、構造化されたレポートやプレゼン資料に再編集することが重要です。
- レポート形式での要点整理
目的/インタビュイーの属性/主な知見/ビジネス示唆といった軸で整理することで、複数部署でも理解しやすい共有資料になります。 - 社内会議や戦略検討時の資料として活用
例:市場参入の可否判断、商品ローカライズ戦略、アライアンス検討など
また、複数のインタビュー結果を横並びで分析することで、業界全体の構造的な傾向や意見の分布が見えてきます。これは定量データだけでは捉えきれない「判断の背景にある文脈」を明確化するのに役立ちます。
② 社外への発信・ブランディングにも活かせる素材へ
得られたインタビュー情報は、社外向けコンテンツとしての再活用も可能です。とくに、BtoB企業にとっては信頼性や専門性の裏付けとして機能するため、さまざまな広報・マーケティング施策と親和性があります。
- ホワイトペーパー、業界レポートへの引用
現地のエキスパートの声を用いることで、読み手にとって「信頼できる一次情報」としての価値を付加できます。 - SNSやWebコンテンツでの発信
短く印象的なコメントを抜粋し、グラフィックと合わせてSNSに投稿することで、専門性と現地感覚の両立を図った発信が可能です。 - 現地語への翻訳・多言語対応
ローカル市場向けに翻訳・調整したうえで発信することで、**「現地理解のある企業」**としてのブランディング効果を高めることもできます。
③ エキスパートインタビューから得られた3つの実践事例
弊社グローハイが支援したクライアント企業における具体的な活用例を3つ紹介します。
① 玩具メーカーの事例
状況:
弊社クライアントである日本の玩具メーカーは、アメリカ進出を見据えて現地での需要を把握する必要がありました。そこで、現地のおもちゃ業界で企画・販売に携わった経験を持つ人材にインタビューを実施しました。
インタビュー:
アメリカのおもちゃ業界で企画・販売経験を持つ人材に対し、以下の点を中心に詳細にヒアリングを実施しました。
- 消費者が重視するポイント(安全性・教育性・デザイン性など)
- 現地の販路で有効な販売手法
についてヒアリング。
結果:
その結果、日本国内で通用していたデザインやプロモーションの手法をそのまま持ち込むのではなく、アメリカの消費者が共感しやすいテーマ性や販売チャネルに合わせて調整する必要があることが明らかになりました。これにより、クライアントは現地に適した商品企画の方向性を得ることができました。
② 製造業の事例
状況:
弊社クライアントである製造業の企業は、アメリカ市場に進出するかどうかを判断する段階にありました。自社の製品に現地需要があるのか不透明だったため、潜在的な顧客となり得る企業の担当者や業界団体関係者に直接コンタクトを取り、ヒアリングを行いました。
インタビュー:
潜在的な顧客企業の担当者や業界団体関係者に対し、以下の点を中心に詳細にヒアリングを実施しました。
- 現場での具体的な業務課題
- 既存製品への不満
- 日本製品を採用する際に求める条件
を中心にヒアリング。
結果:
インターネットや公開資料では得られない、実際のユーザー視点でのフィードバックを得られたことで、製品をそのまま持ち込むのではなく、仕様の一部をローカライズする必要性が浮き彫りになりました。さらに、「同製品がアメリカ市場で受け入れられる見込みがあるか」という経営上の判断に直結する情報を確保できました。
③ ソフトウェア企業の事例
状況:
弊社クライアントであるソフトウェア企業は、日本国内で高いシェアを誇る業務アプリケーションをアメリカで展開するにあたり、幅広い業界に通用するのか、それとも特定業界に特化すべきかを判断する必要がありました。特に、金融や医療など規制やニーズが大きく異なる分野でどのように受け入れられるかが課題でした。
インタビュー:
金融業界・医療業界など異なる分野の実務担当者に対し、以下の点を中心に詳細にヒアリングを実施しました。
- 日常業務でどのようなアプリやシステムを使用しているか
- 既存システムに対する不満や改善ニーズ(処理速度、ユーザビリティ、サポート体制など)
- 新しいソフトを導入する際に重視する条件(セキュリティ基準、既存システムとの連携、現場での操作性)
- 導入検討時に意思決定に関わるのは誰か(現場担当者/経営層)
結果:
結果として、営業活動での訴求ポイントが具体化し、開発ロードマップに反映できる情報資産を獲得することができました。
このように、エキスパートインタビューを通じて得られる情報は、単なる調査結果にとどまらず、市場参入可否の判断材料・製品のローカライズ方針・営業メッセージ設計といった実務レベルに直結する意思決定を支える役割を果たしています。
第5章:海外調査としての価値と投資対効果の高め方
エキスパートインタビューを含む海外調査は、限られた予算の中で行われることも多く、「どれだけリターンが得られるか」という視点が常に求められます。本章では、インタビュー調査を“一回限りの情報収集”で終わらせず、資産として循環させる設計のポイントを中心に、外部パートナーとの連携や多言語・多文化対応の工夫も含めて、投資対効果(ROI)を高める具体的な方法を紹介します。
① 単発調査に終わらせない情報活用の循環設計
調査結果を最大限に活用するには、「調査 → 活用 →再利用 →社内定着」という循環型の設計が欠かせません。以下のような視点を持つことで、調査の成果を長期的に活かすことができます。
- 活用範囲の拡張を前提とした実施設計
インタビューの質問設計段階で、社内活用・対外発信・教育素材化などの展開先を見据えておくことで、汎用性の高い素材が得られます。 - 定期的な再利用とアップデートの仕組み化
一度の調査で終わらず、「半年後に再ヒアリング」「別セグメントで同様の質問」など、比較・経年変化を見据えた設計ができれば、中長期での価値も大きくなります。 - 社内での知見共有・ナレッジ管理の仕組み
社内ポータルやプロジェクトドキュメントにまとめて蓄積・タグ付けしておくことで、後から別部署や別テーマでの再活用が可能になります。
② 外部調査会社・ローカルパートナーとの連携
エキスパートインタビューの実施にあたって、すべてを自社内で完結させるのは難しいのが現実です。信頼できる調査会社や現地パートナーとの連携は、成功率と精度を高めるうえで極めて重要です。
- 現地事情に詳しい調査会社の活用
現地の業界構造や文化的前提に即した質問設計、対象者選定、アプローチ方法など、実務面での支援はプロフェッショナルに任せる方が確実です。 - ローカルパートナーとの橋渡し的協業
現地で信頼されている中小規模のエージェントや業界団体と連携することで、潜在的なキーパーソンへの接触やオープンな対話が成立しやすくなります。 - コスト管理の透明性と中長期的関係の構築
一回ごとの発注ではなく、複数国・複数案件での継続的な連携を前提とすることで、調査コストの抑制やナレッジ共有の効率化にもつながります。
③ 多言語・多文化への対応と編集の工夫
海外調査においては、言語や文化の違いが“誤解”や“空振りの質問”を生みやすいリスクがあります。得られた情報の質と精度を維持するためには、以下のような工夫が欠かせません。
- 通訳者・翻訳者との連携を調査前から設計に含める
逐語通訳や録音ベースの翻訳ではなく、調査の意図や専門用語の背景まで理解した通訳者/翻訳者と協力することが、情報のブレを防ぎます。 - 文化的背景を加味した質問と表現
たとえば「意思決定者」という概念ひとつとっても、欧米とアジアで捉え方が異なるケースがあります。事前の文脈理解と、表現のチューニングが必要です。 - 報告書・社内資料の多言語対応と文体の最適化
単なる翻訳ではなく、現地スタッフや他国の社内関係者にとっても読みやすい表現や構成に再編集することで、調査の価値がより広く伝わります。
このように、エキスパートインタビューを含む海外調査は、設計段階から活用・再利用・多言語対応までを意識することで、単なる情報収集ではなく中長期的な価値を生む資産へと昇華させることができます。
グローハイでは、こうした海外調査の価値を最大化するために、以下のような支援を提供しています。
- 定性調査と定量調査を柔軟に組み合わせた分析と提案
- 現地に精通したマーケティング担当者による、的確な顧客調査と情報収集
- 多様な業種・業態、幅広い調査手法に対応した豊富な実績
詳細なサービス内容や導入事例については、以下のページをご覧ください。
海外向け市場調査・コンサルティングサービスページ:https://glohai.com/research-consulting
おわりに
海外市場への挑戦において、成功の鍵を握るのは、机上のデータだけでは見えてこない「現地のリアル」をどれだけ深く理解できるかという点です。エキスパートインタビューは、そのギャップを埋め、事業判断や発信活動に厚みを持たせるための有効な手段として、多くの企業にとって不可欠な調査手法となりつつあります。
本記事では、エキスパートインタビューの基本から、実施のポイント、得られた知見の活用方法、投資対効果を高める工夫までを体系的に紹介しました。調査そのものに価値があるのではなく、それをどう活かし、再利用し、資産として蓄積していくかが、本質的な成果を左右します。
今後、海外展開を検討・推進される企業が、単なる情報収集を超えて、「戦略」と「発信」の質を高めるための一手として、エキスパートインタビューを効果的に活用されることを願っています。
グローハイでは、今回紹介したエキスパートインタビュー支援のほか、市場調査、SNS・インフルエンサーマーケティング支援、BtoBオンライン展示会「VirtualExpo」への出展支援、海外法人設立、代理店開拓まで、一気通貫でサービスをご提供しております。
海外市場での事業拡大をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
グローハイのサービス詳細については、こちらのリンクをご覧ください:https://glohai.com/ お問い合わせは、こちらからどうぞ: https://glohai.com/contact
■グローハイでは海外オンライン展示会「VirtualExpo(ヴァーチャル・エキスポ)」の出展をサポートしています。
VirtualExpoは機械、建築、造船、医療、農機、航空の6分野における製造業のBtoB専門オンライン展示会です。
欧州や北米、南米、さらにはアジア、中東アフリカ等にもリーチ可能なオンラインによるビジネスマッチング・プラットフォームです。欧州バイヤーが半数以上を占めるVirtualExpoに出展することで、欧州を始めとする世界各国・地域への販路開拓が可能となります。
出展するには英語対応が必要で、グローハイでは日本企業様のVirtualExpoの営業窓口を担っております。