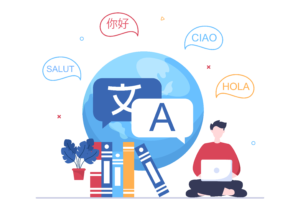こんにちは!グローハイの海外進出サポートチームです。
私たちは、日本企業のアメリカ市場進出を支援する専門チームとして、現地調査から戦略立案、マーケティング施策までを一貫してサポートしています。
特に近年では、「現地の生活者が本当に求めていること」を正しく理解することが成功の鍵となっており、その手段としてフォーカスグループインタビュー(FGI)を導入する企業が増えています。
この記事では、アメリカで一般的に使われているFGIの基礎から、日本企業が活用する際のポイント、そして私たちが支援した実例までを紹介します。
アメリカ市場で確かな成果を上げるために、“現地の声を聞く”第一歩として、ぜひ参考にしてください。
■グローハイでは海外オンライン展示会「VirtualExpo(ヴァーチャル・エキスポ)」の出展をサポートしています。
VirtualExpoは機械、建築、造船、医療、農機、航空の6分野における製造業のBtoB専門オンライン展示会です。
欧州や北米、南米、さらにはアジア、中東アフリカ等にもリーチ可能なオンラインによるビジネスマッチング・プラットフォームです。欧州バイヤーが半数以上を占めるVirtualExpoに出展することで、欧州を始めとする世界各国・地域への販路開拓が可能となります。
出展するには英語対応が必要で、グローハイでは日本企業様のVirtualExpoの営業窓口を担っております。
https://glohai.com/virtualexpo/embed#?secret=2sKCxOWYGe#?secret=TWEuwM8BPi
目次
第1章|フォーカスグループインタビューとは?基本概念と特徴
- フォーカスグループとは何か
- 定量調査との違い
- メリットとデメリット(深い意見収集 vs バイアスのリスク)
- 活用される場面(商品開発/広告テスト/UX調査など)
第2章|なぜアメリカではフォーカスグループが重視されているのか
- アメリカのマーケティング文化と歴史的背景
- 多様性社会における定性調査の重要性
- 実施体制の整備(専門ファシリテーター/専用施設)
- 米国企業での代表的な活用事例(FMCG・映画業界など)
第3章|フォーカスグループの実施ステップと成功のコツ
- 目的設定とターゲットの選定
- 質問設計とモデレーション
- オンラインと対面の使い分け
- データ分析と活用法
第4章|グローハイでのフォーカスグループ活用事例
- 日本企業がアメリカ進出時に直面する課題
- 玩具メーカーでの活用事例(消費財)
- BtoB製造業での事例(ソフトウェア設計)
- UI評価を目的とした事例(業界非公開)
- 成功の要因とグローハイの強み
第5章|日本企業がフォーカスグループを活用する際のポイント
- 日本での普及状況と課題
- 効果を高めるための3つの工夫
- ファシリテーターの選定
- 事前リサーチとの連携
- オンライン活用による壁の突破
- 海外市場調査への応用の可能性
おわりに
第1章|フォーカスグループインタビューとは?基本概念と特徴
フォーカスグループとは何か
フォーカスグループインタビュー(Focus Group Interview)とは、特定のテーマについて、6〜8名程度の参加者がグループ形式で意見交換を行う定性調査手法です。モデレーター(司会進行役)が議論をリードし、参加者の率直な意見や感情、価値観を引き出すことを目的としています。
この手法は、数値では測れない「なぜそう思うのか」「どう感じるのか」といった消費者の深層心理やインサイトを明らかにするために活用されます。
メリットとデメリット(深い意見収集 vs バイアスのリスク)
メリット
- 参加者同士の会話による相互刺激で、多様な意見が自然に引き出されやすい
- 消費者の表面に出にくい感情や潜在的ニーズを把握できる
- 新商品や広告案などに対するリアルな反応をその場で観察できる
デメリット
- サンプル数が少なく、結果を一般化しにくい
- モデレーターの進行次第で結果が偏る(バイアス)可能性がある
- 発言力の強い参加者に議論が左右されることがある
そのため、目的や課題に応じて、定量調査との併用が推奨されます。
活用される場面(商品開発/広告テスト/UX調査など)
フォーカスグループインタビューは、主に以下のようなマーケティング場面で活用されています。
- 新商品開発のアイデア探索やコンセプト評価
- パッケージや広告コピーの印象テスト
- ターゲット層のライフスタイルや価値観の把握
- アプリやWebサービスのUX評価
- ブランドイメージのギャップや課題抽出
特に、具体的な方向性がまだ定まっていない初期フェーズでのインサイト収集に適しており、商品やサービスの開発方針に深い示唆を与えるツールとして注目されています。
第2章|なぜアメリカではフォーカスグループが重視されているのか
アメリカのマーケティング文化と歴史的背景
フォーカスグループという手法は、第二次世界大戦後のアメリカで本格的に発展しました。特に1940年代、心理学者のエルンスト・ディヒター(Ernest Dichter)や社会学者のポール・ラザースフェルド(Paul Lazarsfeld)らが、消費者の無意識的な動機を探るための調査として活用し始めたのが始まりです。
アメリカは早くから「顧客中心主義(Customer-Centric)」を掲げており、企業活動の中にマーケティングリサーチが深く組み込まれている文化があります。企業は製品開発や広告制作の前に、消費者の意見をしっかりと調査し、方向性を定めるのが一般的です。
この中で、「なぜそう思うのか」を掘り下げる定性調査(Qualitative Research)は、特に広告やブランディングの分野で重視されてきました。
多様性社会における定性調査の重要性
アメリカは、人種・宗教・年齢・性別・価値観などが極めて多様な社会です。定量調査によって数字上の傾向をつかんでも、背景にある理由や文化的なニュアンスは読み取れないことが多いため、定性調査の必要性が高くなります。
例えば、同じ商品でも、アジア系・ヒスパニック系・白人・アフリカ系アメリカ人の間で感じ方や購買動機が大きく異なる場合があります。そのため、少人数で深く話し合うフォーカスグループが、非常に有効なリサーチ手法として確立されてきました。
また、LGBTQ+やZ世代など新しい価値観を持つセグメントへの理解にもフォーカスグループは活用されており、広告制作やキャンペーン立案におけるミス(カルチャーエラー)を防ぐ手段にもなっています。
実施体制の整備(専門ファシリテーター/専用施設)
アメリカでは、フォーカスグループの実施に関して高度な専門職能とインフラが整備されています。
- モデレーター(ファシリテーター)は、調査設計、参加者誘導、発言分析に精通した専門の職種として確立されています。
- 都市部には専用のフォーカスグループ施設が多数あり、一方通行のミラー付き観察室や録音・録画設備、リアルタイム分析ツールなどが備えられています。
- 最近では、Zoomや専用プラットフォームを用いたオンライン・フォーカスグループも一般化しており、地理的制約を超えてリーチできる体制が整っています。
このように、企業が当たり前のようにフォーカスグループを活用できる環境があることも、アメリカでこの手法が根づいている理由のひとつです。
米国企業での代表的な活用事例(FMCG・映画業界など)
フォーカスグループは、以下のような分野で特によく活用されています。
- FMCG(Fast Moving Consumer Goods:日用消費財)業界
たとえばP&Gやユニリーバなどの大手企業は、新製品のパッケージ・香り・ネーミングの印象などを発売前にテストします。消費者の「共感できる言葉」や「嫌悪感を感じる要素」などを抽出し、製品改善につなげています。 - 映画業界・TV業界
映画の予告編やエンディングの反応をフォーカスグループで事前確認することは、ハリウッドではごく一般的です。過去には、テスト視聴後にストーリーを変更した例も複数あります。 - IT・テック企業(Google、Metaなど)
UX(ユーザー体験)の評価や、新機能リリース前のユーザー反応確認のために、ターゲット層を絞ったフォーカスグループを定期的に実施しています。
このように、意思決定の前段階で消費者の“感情”や“意見”を把握する習慣が根づいているのが、アメリカの大きな特徴です。
第3章|フォーカスグループの実施ステップと成功のコツ
1. 目的設定とターゲットの選定
まずは「何を明らかにしたいか」を明確にします(例:新商品の印象、広告コピーの反応など)。
次に対象者を選定します。年齢、性別、購入経験などから課題に関係の深い層を選び、6~8人程度で構成するのが一般的です。
2. 質問設計とモデレーション
質問はオープンなものから始め、徐々に深掘りしていくのが基本です。
モデレーターは、話しやすい空気をつくりながらも、話題がずれないよう調整します。
強い発言者に引っ張られないよう、全員が話せる場をつくることが成功の鍵です。
3. オンラインと対面の使い分け
| 方法 | 特徴 |
| 対面 | 表情や空気感が読みやすく、商品体験を伴う調査に向く |
| オンライン | 地域を問わず参加者を集めやすく、コストも低い |
近年はオンライン形式の活用が増加していますが、対象層や目的に応じて使い分けが必要です。
4. データ分析と活用法
録音や文字起こしをもとに、共通意見や特徴的な発言を抽出します。
そこから、「どこに不満があるか」「何に強く共感しているか」などを分析し、商品開発や広告の改善につなげます。
結果は、社内の意思決定や、定量調査の設計にも活用されます。
このように、フォーカスグループは事前準備・進行・分析を丁寧に行うことが成果を左右します。単なる会話ではなく、ビジネスに直結するインサイトを得るための重要なプロセスです。
第4章|グローハイでのフォーカスグループ活用事例
グローハイでは、アメリカ進出を目指す日本企業の支援の一環として、現地の消費者やユーザーに向けたフォーカスグループインタビュー(FGI)を実施しています。ここでは実際の活用事例をもとに、その有効性をご紹介します。
日本企業がアメリカ進出時に直面する課題
日本企業が米国市場に製品を展開する際には、次のような課題に直面します。
- 日本での常識がアメリカでは通用しない(価値観や購買行動の違い)
- パッケージや色、仕様などが現地ニーズとズレている
- 実際の使用シーンや導線にギャップがある
こうした「文化・行動の違い」を理解するには、定量調査だけでは不十分であり、現地の“声”を深く掘り下げる定性調査が不可欠です。
大手玩具メーカーでの活用事例(消費財)
ある日本の玩具・育児用品ブランドでは、新しいベビー用商品をアメリカ市場に投入するにあたって、現地の親のニーズを把握するためにFGIを実施しました。
- 実施方法:5人前後の母親を集め、ディスカッション形式でグループインタビュー
- 質問内容:育児中の困りごと、同類製品の使用感、どのようなパッケージに安心感や魅力を感じるか
議論の中では、日本とアメリカの育児スタイルや価値観の違いも浮き彫りになりました。たとえば、親子の寝方など、日常的な育児習慣にも文化差が見られました。
こうした違いを踏まえ、パッケージデザインや訴求ポイントを製品設計にも反映。
得られた消費者インサイトは、広告制作や販売戦略にも波及し、導入後のブランド評価にも好影響を与えました。
BtoB製造業での事例(ソフトウェア設計)
また、あるBtoBの製造業向け大手ソフトウェア企業では、北米のエンジニアが現在どのようなツールを使い、どこに課題を感じているのかを探るために、フォーカスグループを活用。
- ユーザー企業から現場のエンジニアを集め、使用実態・ニーズ・理想のUI設計などについて自由に話してもらう場を設定
- その声をもとに新製品を開発
特にこのような技術系分野では、少人数の濃密な議論から得られるニッチな要望が、製品差別化の鍵になることが多いです。
UI評価を目的とした事例(モバイル端末)
さらにある大手企業の案件では、アメリカと日本での「色の認識」「ボタン配置」など、ユーザーインターフェースの感じ方の違いを検証するために、現地ユーザーにサンプルを実際に使ってもらい、反応を観察する調査を行いました。
- 実物を用いたテストとインタビューを組み合わせて実施
- 「言語化しにくい違和感」など、深いフィードバックが得られた
- 結果として、米国向けUIの再設計と改善に直結しました
成功の要因とグローハイの強み
これらの事例に共通しているのは、単なる意見収集にとどまらず、文化・言語・価値観のギャップを「実際の使用者の声」から把握したことです。
グローハイは、アメリカで一般的なマーケティングリサーチ会社と同様に、現地での人材確保、英語でのファシリテーション、オンライン・オフライン両対応の実施体制を整備しており、実施後のレポーティングまで含めて、日本の企業様から高い評価を得ています。
第5章|日本企業がフォーカスグループを活用する際のポイント
日本での普及状況と課題
フォーカスグループインタビュー(FGI)は日本でも導入されているものの、定量調査(アンケート調査など)に比べて活用頻度は高くありません。その理由のひとつに、日本人特有の「空気を読む」文化があります。
集団の中で自分の意見を率直に述べることに抵抗を感じる人が多く、本音を引き出すのが難しいという課題が指摘されています。
また、企業側も「数値データの方が説得力がある」と考える傾向が強く、定性調査は補助的に扱われるケースが多いのが実情です。しかし、商品開発やマーケティング戦略の初期段階では、消費者の“言葉にならない感覚”を掘り下げる定性調査が不可欠です。
効果を高めるための3つの工夫
日本企業がFGIを有効に活用するためには、いくつかの工夫が必要です。
・ファシリテーターの選定
参加者の緊張を和らげ、意見を自然に引き出すためには、進行に慣れたファシリテーターの存在が不可欠です。特に日本では、発言の少ない参加者にも丁寧に声をかけて意見を引き出せる、聞き役としてのスキルが高い人材が望まれます。
社内の人間が進行を担当すると、参加者が「本音を言いにくくなる」傾向もあるため、中立的な外部ファシリテーターの起用が効果的です。
・事前リサーチとの連携
FGIはあくまで定性調査であるため、事前に簡単なアンケートやインタビューを実施し、参加者の背景や興味関心を把握しておくことで、より深い議論が可能になります。
また、事後に定量調査と組み合わせることで、得られたインサイトの「裏付け」を取ることができ、戦略への説得力が高まります。
・オンライン活用による壁の突破
近年はZoomなどを使ったオンライン・フォーカスグループの活用が進んでおり、日本でも有効な手段です。
自宅からの参加によりリラックスした雰囲気が生まれ、対面よりもむしろ本音が出やすくなるケースもあります。また、地方や海外の生活者にもアプローチできるため、調査の幅を広げる手段として有効です。
海外市場調査への応用の可能性
フォーカスグループは、海外市場調査においても極めて有効な手段です。特に文化・言語・習慣が大きく異なる国に製品やサービスを展開する場合、現地消費者の「感じ方」や「常識」を理解するには、定性調査が欠かせません。
グローハイのように、現地での調査環境や実施体制を整えているパートナーと連携すれば、日本企業でも手軽に現地向けのFGIを実施できます。
実際に、ローカライズ戦略や製品仕様の最適化、広告メッセージの改善に直結した成果も多く見られます。
日本国内でも海外展開においても、フォーカスグループは消費者理解を深めるための有効なマーケティング手法です。定量データでは捉えきれない「声にならない声」に耳を傾けることで、より的確な意思決定につなげることができます。
おわりに
フォーカスグループインタビューは、数値では捉えきれない顧客の本音や行動の背景を明らかにできる貴重な手法です。とくに市場環境や文化の異なるアメリカにおいては、その価値がより高く発揮されます。
日本企業がグローバル展開を目指すうえでも、こうした定性調査を適切に活用することで、より現地に合った商品開発・プロモーション設計が可能になります。
グローハイでは、アメリカ現地でのフォーカスグループ実施や分析、レポート作成まで一貫してサポートしています。
実際の生活者の声に耳を傾け、より深い市場理解を得たい企業にとって、有効な選択肢となるはずです。
グローハイでは、今回紹介したアメリカ現地でのフォーカスグループ実施や分析、レポート作成までの一貫したサポートの他、現地市場の調査、マーケティング支援、営業活動のサポートまでを一気通貫でご提供しております。
アメリカ市場での事業拡大をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
グローハイのサービス詳細については、こちらのリンクをご覧ください:https://glohai.com/
お問い合わせは、こちらからどうぞ: https://glohai.com/contact
■グローハイでは海外オンライン展示会「VirtualExpo(ヴァーチャル・エキスポ)」の出展をサポートしています。
VirtualExpoは機械、建築、造船、医療、農機、航空の6分野における製造業のBtoB専門オンライン展示会です。
欧州や北米、南米、さらにはアジア、中東アフリカ等にもリーチ可能なオンラインによるビジネスマッチング・プラットフォームです。欧州バイヤーが半数以上を占めるVirtualExpoに出展することで、欧州を始めとする世界各国・地域への販路開拓が可能となります。
出展するには英語対応が必要で、グローハイでは日本企業様のVirtualExpoの営業窓口を担っております。
https://glohai.com/virtualexpo/embed#?secret=2sKCxOWYGe#?secret=TWEuwM8BPi